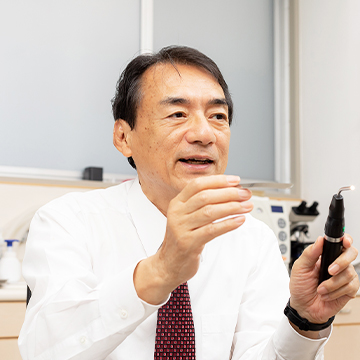- HOME>
- 嘔吐した時
子どもの嘔吐について

嘔吐とは、胃の内容物が意図せず強制的に口から排出される状態です。
時には胃液だけでなく、十二指腸液や胆汁が混ざることもあります。お子さまの嘔吐の主な原因としては、ウイルス性胃腸炎が最も多く、その他にも食中毒、胃食道逆流症などがあります。
受診の目安
受信の目安
- 6時間以上、嘔吐が続いている
- 吐物がコーヒーかす状や緑色である
- 水分補給ができない状態が続いている
- 口内が乾いている、汗をかいていない
- おしっこの量が明らかに減少している
- 顔色が悪く、ぐったりしている
- 咳、発熱、発疹を伴う
- 息苦しそうにしている
- 便に血が混じっている
- 1週間以内に頭を打っている
- お腹を激しく痛がっている
特にこのような場合には緊急受診(救急外来)を受診しましょう
- 吐物に血液や緑色の胆汁が混じっている
- 頭部打撲後24時間以内の嘔吐
- 嘔吐と下痢を繰り返し、脱水症状がある
- けいれんを伴い、意識がもうろうとしている
- 半日以上おしっこが出ていない
- 唇や舌が乾燥している
繰り返す嘔吐から考えられる主な疾患
急性胃腸炎
ウィルスや細菌に感染して、嘔吐、下痢、腹痛などの症状を起こします。多くの場合、嘔吐は1~2日で、熱が出ることもあります。下痢は数日から10日程度続くこともあります。
| ウィルス性 | ロタ、ノロ、アデノなどウィルス感染により起こります。 嘔吐や発熱は比較的早めに落ち着きます。 |
|---|---|
| 細菌性 | カンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラなどにより起こります。 強い腹痛、高熱や血便が出ることもあります。 |
周期性嘔吐症
自家中毒とも呼ばれますが、2~10歳の子どもに多く、体内のケトン体が過剰に生成される代謝異常です。周期的に嘔吐発作を繰り返し、口臭(アセトン臭)を伴うことが特徴的です。
腸重積症
腸重積症は腸の一部が別の部分に滑り込む疾患で、主に生後3ヵ月~3歳の乳幼児に多く見られます。突然の激しい腹痛と嘔吐が特徴で、乳児では説明のつかない大泣きとぐったり状態を繰り返します。粘血便を伴うこともあり、早期の診断と治療が必要です。
咳込み嘔吐
鼻炎などによる喉への痰の垂れ込みや喘息発作などによる咳こみが強いときにも嘔吐することがあります。咳が和らぐように、水分をこまめに摂ったり、体を起こして寝かせましょう。
その他の原因
幽門狭窄症、髄膜炎、脳腫瘍や頭部外傷なども嘔吐の原因となることがあります。
家庭でできる対処のポイント
姿勢と安静
嘔吐後は体を起こし、背中を優しくさすりましょう。抱っこする場合は縦抱きにし、体を揺らさないよう注意します。車酔いや頭痛による嘔吐の場合は横になって安静にすることをおすすめします。
水分補給
嘔吐後しばらく様子を見て、吐き気が落ち着いてから水分補給を開始しましょう。常温の経口補水液、母乳やミルクを少量(スプーン1杯)から始めます。いずれも水で薄める必要はありません。3時間以上嘔吐がなければ、徐々に量を増やしていきましょう。
食事の再開
嘔吐が落ち着くまで無理に食べさせる必要はありません。症状が落ち着いたら、本人が食べやすいものから少量ずつ与えましょう。脂っこい料理や糖分の多いお菓子、香辛料の多い料理は避けるのが良いでしょう。
吐いたものの処理
吐いたものは、できるだけ早く処理をしてください。100倍に薄めた塩素系漂白剤を浸したペーパータオルで拭き上げてください。その後、30秒から1分ほどかけて丁寧に手を洗いましょう。
くまがいこどもクリニックの対応

当クリニックでは、お子さまの嘔吐の原因を的確に診断し、適切な治療をおこないます。
- 嘔吐の性状や頻度、随伴症状からの原因特定
- 脱水症状の評価と適切な水分補給指導
- 必要に応じた検査(血液検査、尿検査、超音波検査など)
- 家庭での適切なケア方法の説明
- 経過観察のポイントと再受診の目安
お子さまの嘔吐でご心配の際は、症状の程度にかかわらず、お気軽にご相談ください。特に繰り返す嘔吐や、上記の受診目安に当てはまる場合は、早めの受診をおすすめします。