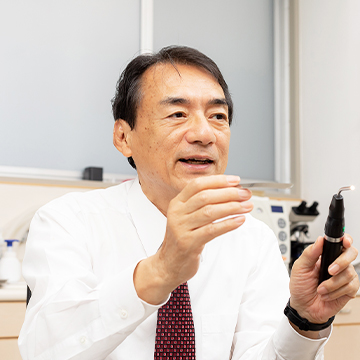- HOME>
- 離乳食・補完食
離乳食=補完食とは?

赤ちゃんは生後5〜6か月ごろになると、母乳やミルクだけでは成長に必要な栄養をすべてまかなえなくなってきます。そこで始めるのが「離乳食」、国際的には「補完食」と呼ばれる食事です。
離乳といっても「乳から離れる」ことではなく、「母乳やミルクを続けながら、不足する栄養を補っていく」という意味があります。家庭の食事を赤ちゃんの発達に合わせてやわらかく調理し、少しずつ「家族の食卓」になじんでいきます。
始めるタイミング
離乳食を始める目安には、次のようなサインがあります。
- 首がしっかり座っていること
- 支えれば座れるようになってきたこと
- 食べ物に興味を示すこと
- スプーンを口に入れても舌で押し出さなくなってきたこと
これらがそろってきたら、5〜6か月ごろを目安に離乳食をスタートしてみましょう。
母乳やミルクは減らさなくてよい
「離乳食が進むために母乳やミルクを減らさなければならないのでは」と心配される方もいますが、その必要はありません。
補完食を始めても、母乳やミルクは引き続き必要カロリーの多くを担い、免疫物質も含む大切な栄養源です。
無理に減らすと体重が増えにくくなることもあるため、欲しがるときに欲しがるだけあげてください。
おかゆは濃さが大事
離乳食のスタートで使うおかゆは、水分が多すぎると栄養が薄まり、赤ちゃんの小さな胃では必要なカロリーをとることができません。スプーンにのせても落ちにくい、ペースト状の濃さを目安にしましょう。最初は5倍がゆ小さじ1程度から始め、慣れてきたら野菜やたんぱく質を少しずつ加えていきます。
補うべき大切な栄養素
補完食の最大の目的は、不足してきた栄養を補うことです。特に意識したいのは以下です。
- 鉄:赤身の肉や魚、豆製品、卵黄など
- 亜鉛:肉、魚、豆腐など
- カルシウム:乳製品、小魚、野菜など
- ビタミンA・C・葉酸:野菜や果物
赤ちゃんは生まれたときに「貯蔵鉄」を持っていますが、生後6か月頃には使い切ってしまいます。そのため、食事から鉄をしっかり補う必要があります。従来「白身魚から」と言われていましたが、栄養学的な根拠は乏しく、鉄を含む赤身の肉や魚を少量から導入する方が理にかなっています。
ベビーフードも上手に活用
すべてを手作りする必要はありません。市販のベビーフードを適切に使えば負担を減らせます。ただし保存や食べ残しに注意し、開封後は速やかに使用するようにしましょう。また、家族の味噌汁や煮物を味付け前に取り分けてつぶすなど、取り分けアレンジを併用するのもおすすめです。
回数や量は月齢よりも発達に合わせて
「〇か月だから何回・何グラム」という進め方は、あくまで目安です。実際には赤ちゃんの発達や食べる様子に応じて進めることが大切です。
- 食べ物をゴックンできるようになったら → 1日1回からスタート
- 舌でつぶすことができるようになったら → 少しずつ回数や種類を増やす
- 手づかみ食べに興味が出てきたら → 自分で食べる練習を取り入れる
無理に量や回数を増やそうとせず、赤ちゃんができるようになったことに合わせて進めることが大切です。離乳食の進み方には個人差があり、焦る必要はありません。大切なのは 量ではなく赤ちゃんの表情や反応を見ることです。
補完食が進まないとき
- 無理に食べさせると、かえって嫌がることがあります
- 手づかみ食べを取り入れると、自分のペースで食べやすくなることがあります
- 薄味の場合、味を少し濃くすると食べてくれることがあります
- 食事は「学びの時間」と考え、楽しい雰囲気を大切にしましょう
ただし、生後9か月を過ぎても母乳やミルク以外をまったく受け入れない場合は、小児科で発達や栄養状態を確認することをおすすめします。
手づかみ食べのすすめ
赤ちゃんは「自分で食べたい」という気持ちが芽生えると、手づかみ食べを始めます。6か月ごろで約4割、8か月ごろには9割の子どもが始めるといわれています。
最初は生のにんじんやセロリなどの固い野菜を棒状にして渡すとよいでしょう。噛み切れないため安全に練習ができます。
慣れてきたら、煮た野菜や肉・魚を1cm角に切り、歯ぐきでつぶせる柔らかさに調理して与えます。ただし、必ず大人がそばで見守り、窒息には十分注意しましょう。
乳幼児で注意する食品
- はちみつ:1歳未満は禁止。加熱しても芽胞は死滅しません。自家製野菜ジュース、コーンシロップ、**真空パック詰め食品(非加圧加熱殺菌)**もボツリヌス症のリスクがあります。
- ぎんなん:3歳未満で10個以上食べると嘔吐・けいれんなどを起こすことがあります。
- 粉ミルク:溶かした後2時間以上室温に放置したものは与えない。
- 生卵:サルモネラ菌のリスクがあるため十分加熱を。生食は3歳から。
- 加熱不十分の肉や魚介類:カンピロバクター、O-157などのリスク。必ず十分に加熱し、生食用と加熱用で箸を分ける。
- 生の魚介類:腸炎ビブリオやアニサキスのリスク。寿司・刺身は乳幼児期には控えるのが安心。
- カキなどの二枚貝:ノロウイルスのリスク。必ず加熱してから。
- 古くなった魚:ヒスタミンによる食物アレルギー様症状(じんましん・嘔吐・下痢など)のリスク。新鮮な魚を選び、冷凍保存を。加熱してもヒスタミンは壊れません。
家族と一緒の食卓を楽しみましょう

離乳食(補完食)は特別な食事ではなく、家族の食卓になじむステップです。
大人用に味付けする前に取り分けて工夫すれば、同じメニューを楽しむことができます。
大切なのは「食事の場が楽しいこと」です。保護者がリラックスして食卓を楽しむ姿は、赤ちゃんにとって最高のお手本になります。
離乳食(補完食)は、母乳やミルクをやめるためではなく、不足する栄養を補い、赤ちゃんが「食べることを学ぶ」大切なステップです。
始めるタイミングを見極めながら、鉄を意識した食材を取り入れ、焦らず赤ちゃんのペースで進めていきましょう。困ったときはご相談ください。